これからの生き方に参考にしていこうと、伊能忠敬さんの生き方を学びました。
江戸時代の伊能忠敬さんが日本地図の作成を始めたのは隠居後からだそうです。その後17年にわたり測量を続けます。よほど体力に自信があり、悠々自適の挑戦であったのかと短絡的に思ってしまいます。しかし、常に体力には自信がなかったようです。実際のところ、目標であった地図の完成前に亡くなりました。余裕があるからできる、挑戦できるという考え方は捨てたほうがいいことを教えてくれます。
伊能忠敬さんとは
伊能忠敬(いのう ただなか 1745年<延享2年>~1818年<文政元年>)さんは、江戸時代後期の測量家・地理学者です。日本全国を歩いて測量し、正確な日本地図を作成しました。死後、弟子たちによって、「大日本沿海輿地全図」、日本初の科学的な地図が完成しています。
千葉県佐原市にある伊能忠敬さんゆかりの地
伊能忠敬さんは、佐原の商家に婿入りし、家業を反映させます。このあたりは、風情のある街で有名です。観光客向けに整備されています。街の中を川が流れています。
家督を50歳で譲り、隠居します。
決めていました、次の生き方を
伊能家には多くの書物がありました。教養も商売を広げる力ですので、知識を身につける努力をしていました。その名から、天文暦学に興味を持ち、隠居後はこれを極めようと考えました。
ところで天文暦学とは?
天文暦学とは天文学と歴法を合わせた学問です。江戸時代は、暦を正しく作ることが国家運営に深く関わっていたため、非常に重要な学問とされていました。天文学は星や太陽、月の動きを観察し、計算します。これが日食や月食の予測や、星の位置、時間の計算に必要とされます。暦学とは、観測した天体の動きに基づいて、正確な暦を作る学問です。江戸幕府には天文方という専門部署がありました。
江戸では年下に学んだ?
江戸に出た伊能忠敬さんは、幕府天文方で中心人物であった高橋至時(たかはし よしとき)を師匠とします。年齢差は19歳の年下に学びます。学びたいという好奇心はどんどん飛び込んでいきますね。
高橋至時のもとで天文・測量技術を徹底的に学びます。
伊能忠敬さんが行った測量は、単なる地図つくりではなく、正確な経度・緯度の測定という天文学的観測に基づいた科学的作業でした。
この師弟関係があったからこそ、伊能忠敬さんは無謀ともいえる挑戦、結果を残すことができました。
日本地図については、伊能忠敬さんの弟子たちが師の思いを継いで完成させています。
体が本当に弱かったの?
特定の病名や重病に苦しんでした確かな記録はありません。種々の文献には、「体が弱かった」「体調に不安があった」と推測される記述が残っています。
「50歳にして初めて、自ら鍛錬に努めた」という趣旨の記述があります。具体的には、歩行訓練、食事制限、睡眠の工夫など、当時としては珍しい健康管理とも呼べる自己鍛錬の記録が残されています。
トレーニング?
測量のためには歩きます。歩くだけの体力が必要です。師匠の高橋至時から測量というのは体力勝負の一面もある現実を突きつけられました。伊能忠敬さんは測量を始める前に約1年の歩行訓練を行っています。1日30キロメートルも歩く訓練したこともあり、持久力をつけたことが記録されています。
結論!あなたは何を学んだ?
伊能忠敬さんが偉大な功績を残した日本地図作成を始めたのは隠居後でした。人生50年ともいわれていた時代で次を考えていました。そこに、いくつになっても夢への追及を忘れてはいけないことを学びました。年齢を重ねると、もういいかなと思いがちです。しかし退職後の生きる長さはわかりません。20年も30年も生きる可能性はあります。どうせなら長い時間を想定して、夢を求めていくことは大事ではないでしょうか?
夢があっても、思いだけでは実現しません。実際の測量作業を教えられたとき、技術に加えて、体力・持久力が必要と感じ、準備として歩行訓練に1年かけています。これはすべてに通じます。
徹して体調管理・健康管理していた事実を見逃してはいけません。老化は何もしなければどんどん進みます。自己管理、アンチエイジングの努力が必要です。
結論は
退職して次なる生き方、無職・年金生活で、夢を、そのための準備を、そして支える自己管理をしていきます。


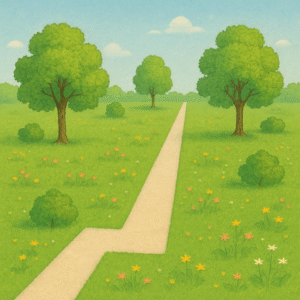



コメント