いつもと形態が違っていますが、ご容赦ください。
目次
- 夢の話が聞こえてきた
- 沈黙が続いたいのは
- これまでのブログ作成の取り組み方
- Windowsとの連携は本当に面倒です
- エディター選び
- AIが扱いやすいマークダウン方式のファイル
- マークダウン方式を扱うObsidian
- WindowsとMacで利用可能
- Google Driveの利用
- 欲張ったためデータが壊れた
- 同期の運用は
- Cursorとの連動
- Cursorで何ができるの
- 夢物語を実現したい
- 背景にツェッテルカステン(zettelkasten)の知的生産術
- メモに残すことに抵抗はありません
- ツェッテルカステンのメモは
- 毎日に終わりには
- 集まってくる情報
- 引用やマークするだけでなく自分の言葉に置き換える
- 音声レコードを充実させる
- さらなるブログ作成に挑戦
夢の話が聞こえてきた
AIが自分のブログを書いてくれるという夢のような話に出会いました。これは本当に便利です。現在のブログ更新の間隔を見ていただくとわかります。なかなかブログ更新ができていません。AIに「このようなテーマで3000文字で書いてください」と指示すると出きあがるらしいんです。凄い時代になりました。

沈黙が続いたいのは
旅行などのイベントがあれば、その新鮮な気持ちを伝えるだけで書くことができます。日常をお知らせするスタイルもみつけられずに、悩んでいたら長い時間が過ぎていった次第です。
さらに先ほどの夢のような話も挑戦できないものか見つけたり、触ったり、試していました。
今日はこれまでの取り組みから新たな取り組みの模様をお伝えしていきます。
これまでの作成の取り組み方
これまで文章はMacのApple memoでブログを作りました。そして、内容を自宅のWindowsでも読み取れる特定のメールアドレスに送って、ブログの形にしています。送った後も内容を訂正を加えながら、写真をつけ加えながらブログにしています。またその出来上がったものを履歴の意味で往復するようにMacに記録しています。
Windowsとの連携は本当に面倒です
実際の作業を文字に起こしましたが、何を言っているか伝わりにくいですが、はっきり言って大変にこの連携が面倒なんです。
Macだけで完結すれば考えなくていい内容ですが、現在の環境はMacそのものは別の場所にほぼ常駐していたため、仕上げは自宅にあるWindowsだったのす。
これも無職・年金生活になれば解消します。それまでの対応です。
エディター選び
まずは昔懐かしのエディタ(テキスト入力)を使おうと、MacでもWindowsでも動くエディタを選べば、同じデータがやり取りするだろうとみつけていました。
AIが扱いやすいマークダウン方式のファイル
いくつかのエディタを試してみた中で、「AIが扱いやすいのはマークダウン方式」ということがわかりました。そのマークダウン方式とは、文章の見出しやリスト、リンクなどを簡単な記号で整理できるテキストフォーマットで、誰でもすぐに読める構造化されたデータになります。AIにとっては、このように見出しや段落、箇条書きが明確に示されていることで、文章の構造や内容を正確に認識しやすいという利点となるそうです。たとえば、「#」がタイトル、「-」がリストにする入力する記号を使うので、これらはすぐに判別できるので、要約や分析などの自動処理がしやすくなります。
マークダウン方式を扱うObsidian
この特徴があるため、多くのAIツールやアプリではマークダウン方式での入出力が標準となっています。実際、Obsidianもマークダウンに特化したエディタなので検索ですぐにヒットしました。AIと連携させることで、文章構造を意識した自動化や編集がとても簡単にできそうです。今回は、新たな取り組みを紹介していきます。
さらにAIと連動すれば、先に出した夢の話も可能のような説明にも触れたため、新しい物好きが好じ、ブログを書くことよりこのソフトを使えるになるほうがおもしろいので、いつの間にか時間をかけてしまったのです。
WindowsとMacで利用可能
ObsidianはWindowsでもMacでも使えるソフトです。同期のためのプラグイン(拡張機能)に、Google Driveを利用する方法を知りました。
Google Driveの利用
ここでWindowsとデータののやりとりにGoogle Driveを利用すると便利なこともわかりました。しかも取り扱うファイルはマークダウン方式のテキストファイルです。フロッピー時代でも使える、容量は極めて少量、データの移動は早くて、メールでのやり取りより手間は楽になりました。
欲張ったためデータが壊れた
当初はMacの他にiPadやiPhoneと、さらに古いMacでiCloudで同期させ、さらにWindowsとの同期をそれぞれのデバイスから同期をかけたため、iCloudは順調に扱えたものの、Windowsの方は同じファイルがコピーされたりと、Macとの同期によってデータが急に消えたり、現象解決にあきらめてしまいました。不安定すぎます。調子に乗りすぎました。
同期の運用は
安全面を重視して、Apple系のデバイスからのデータはこれまで通り、iCloudを利用をして、WindowsにはGoogle Driveに手作業でコピーしての運用にしました。今は安定しています。これさえも自動化はできるはずです。それをみつけたり、可能にしていくのも楽しみの一つです。
Cursorとの連動
さらにObsidianと別のソフトCursorの組み合わせが目に入ってきました。他にはObsidianとClaud codeなど、ObsidianとAIがいろいろと紹介されていました。まだまだAIの利用などに明るくないので、Cursorを利用しながら使用も試みています。Obsidian+Cursor+Claud Codeの方がいいぞとの紹介もありました。欲張りはまた混乱のもとです。一つひとつ理解してからにします。
Cursorで何ができるの
Obsidianのデータをそのまま取り込んで、Cursorで操作をします。例えば、文章の途中で、別の案を入れて書き直してと指示を出せば、新たな提案するテキストが表示され、採用を決めれば、文章そのものを変えることができるのです。
AIが提案してくる文章は自分好みではないので、結局は訂正していくのですが、参考にしています。AIでは自分の文章のイメージを学習し、自分好みの文書まで作成できるようです。研究していきたいです。
夢物語を実現したい
最終的には、テーマや体験をAIに読み込ませ、勝手にブログを作り、量産的にブログを埋め尽くしたいです。
背景にツェッテルカステン(zettelkasten)の知的生産術
Obsidianのファイルのリンクを便利に貼れます。本当の良さはここにあります。この背景には、「ツェッテルカステン」の考え方があります。
これも新たな出会いです。現在向き合っている最中です。知的生産術の一つと考えてください、
ツェッテルカステンの通りに、ノートを整理していけば、あとはノート(ファイル)を並べるだけで一つの文章ができるとの内容に心が動かされたのです。
イベントがなければ書けない今の状況をなんとか壊せないのかと色々と考えていた時に出会ったのが、この考え方です。並べれば、いつの間にかできてしまうなんて大変に魅力的です。これに取り組まない手はありません。
ツェッテルカステンの詳しい内容は
「メモをとれば財産になる 」(日経ビジネス人文庫) ズンク・アーレンス (著)
にあります。興味ある方はこの本で。
メモに残すことに抵抗はありません
ノートにしても、データにしても、メモに残すことにしてきました。手帳へのこだわりも意外とあります。iosのアプリを中心に、最近はアップルメモに原稿や覚え書きを入力してきました。
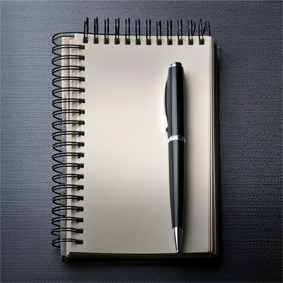
ツェッテルカステンのメモは
ツェッテルカステンのメモの考え方に、メモの形態がいろいろあります。
手帳でも携帯でもいいので、また紙の端切に書いたメモ
今は手帳で手書きにしたものがあります。さらに最近便利にしているものはLINEに入力したものが自動的にObsidianのファイルに登録できるプラグインを見つけましたので、ここに音声入力して登録しています。
書物やネットからの情報提供の文献メモ
永久に残すようなファイルになっていくメモ
現在は、永久という大きな理想で残すというよりも、覚書程度に近い、はっきり言って端切れメモよりもちょっと大事なメモとしてファイルに残しています。
などがあります。
どのメモにもファイルにするときは必ずリンクをはって、タグを残し、たとえ忘れたとしても、ふとしたところから甦り、新たなアイデアの糸口になるかもしれないような仕組みなっています。
これは大事なところかなと思う点は、入力用のテンプレートで統一して引用先等を入力したメモにしていきます。
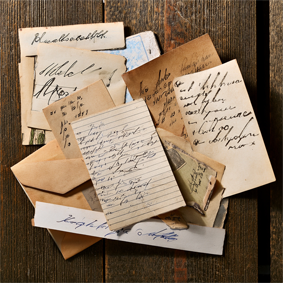
毎日に終わりには
毎日の終わりに行う作業としては、どうでもいいようなメモからこれは大事かなと思ったらファイルにして、さらに関連するリンク、タグ付けをしていきながら、ファイルにしていくことになります。
集まってくる情報
情報も一つのことを考えていると、自然と集まってきます。最近はそんなことを感じます。
引用やマークするだけでなく自分の言葉に置き換える
文献の引用についても、そのまま文字を引用するのではなくて、自分の言葉に置き換えることが重要で、それが理解にもつながるそうです。これはこれまでにない新たな考え方です。そのことに対しての感想はまた別のファイルにして、リンクを貼っておけばいいのです。文献メモとあえて分けるのは、感想が時が経てばまた変化していくこともあるので、引用と感想を一つにしないことに意味があると考えます。
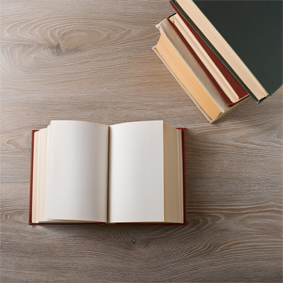
音声レコードを充実させる
そう考えると、意外と便利なのが音声によるレコードによるものです。 ここを充実させていくと、タイプするよりも全然早いので、もっともっと便利になるのかなと思います。 今日購入をしたばかりなので、この具合についてはまた紹介できたらなというふうに考えています。
さらなるブログ作成に挑戦
もっといろんなことに挑戦しながら、その模様をお知らせして、更新の頻度をあげていきます。今回はブログ更新よりも楽しかった新たな出会いの様子をまとめました。
次回も楽しみに

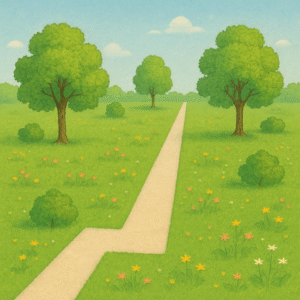



コメント